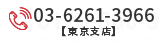接骨院開業 融資の完全ガイド|必要な準備・審査対策など徹底解説

目次
接骨院を開業したいけれど、資金面で不安があるという方は多いのではないでしょうか。
特に初めての開業では、どのように融資を受ければよいか、どんな準備が必要かがわからず、不安になることもあるでしょう。
本記事では、接骨院の開業を目指す方に向けて、融資の必要性や利用者の特徴、よくある失敗例、審査対策、必要書類などをわかりやすく解説します。
この記事を読めば、接骨院開業に向けた融資の全体像がつかめ、何から始めればいいのかが明確になります。
接骨院開業の融資はどんな人が利用しているの?
接骨院の開業に向けた融資は、どのような人たちが利用しているのでしょうか。
ここでは、実際に融資を活用している人たちの特徴について紹介します。
柔道整復師の国家資格を持つ人が多い
接骨院を開業するには、まず柔道整復師の国家資格を持っていることが前提です。
多くの金融機関でも、この資格の有無が融資審査において重要視されます。
資格を持っていることで、事業の継続性や信頼性が高まるため、融資を受けやすくなります。
また、金融機関側も返済能力を判断しやすくなるのです。
整骨院や接骨院での勤務経験がある人が多い
過去に整骨院や接骨院で勤務していた人は、実務経験があるため、開業後も安定した施術を提供できると判断されやすいです。
融資を申し込む際には、これまでの職歴や実績をしっかりアピールすることで、信頼度を高めることができます。
30代〜40代での独立希望者が中心
実際に接骨院を開業する人は、30代〜40代の年代層が中心です。
これは、ある程度の臨床経験を積んでから独立を目指す人が多いためです。
この年代は経験・技術・資金面でのバランスが取れているため、金融機関からも信用されやすい傾向にあります。
開業支援セミナーに参加している人が多い
近年では、開業支援セミナーに参加して情報収集をしている人も増えています。
セミナーでは、融資や事業計画書の作成方法など、実践的な内容が学べます。
セミナーで得た知識や人脈は、融資申請時にも有利に働くケースがあるため、積極的に参加することが望ましいです。
接骨院開業に融資が必要な理由とは?
接骨院を開業するには、なぜ融資が必要になるのでしょうか。
ここでは、主な費用の内訳とその必要性を詳しく見ていきます。
医療機器や施術ベッドの導入に費用がかかるから
開業時には、超音波治療器や低周波治療器などの医療機器、施術ベッド、待合室の椅子など、多くの設備投資が必要です。
こうした設備は新品を購入すると高額になるため、初期費用としてまとまった資金が必要です。
物件取得や内装工事にまとまった資金が必要だから
テナント物件の契約金、保証金、内装工事費用も大きな出費になります。
特に1階路面店など立地のよい場所を選ぶ場合、初期費用は高くなる傾向があります。
開業資金の大半を占めるのがこの物件関連の費用です。
融資を利用しなければ、自己資金だけでは難しいケースも多いです。
開業後すぐに安定収入が得られないから
開業直後は患者数が少なく、売上が安定しない時期が続きます。
そのため、運転資金を確保する目的でも融資が必要です。
収入が軌道に乗るまでの半年〜1年間を想定して、資金計画を立てる必要があります。
広告・集客の初期費用が必要だから
新規開業では、地域に存在を知ってもらうための集客が重要です。
ホームページ制作費、チラシ印刷費、ポスティング、人材採用など多くの費用がかかります。
初期の集客活動は長期的な患者獲得に直結するため、融資を活用してしっかりと投資すべき部分です。
接骨院開業の融資でよくある失敗とその対策

融資を受けたものの、計画通りにいかず失敗してしまうケースもあります。
ここでは、よくある失敗とその対策方法を紹介します。
事業計画書があいまい → 専門家にチェックしてもらう
融資審査では、事業計画書の内容が最も重視されます。
内容が不明確だったり、数字に根拠がない場合は審査落ちのリスクが高まります。
必ず専門家(税理士・中小企業診断士など)にチェックしてもらい、具体性と実現可能性を高めましょう。
自己資金が少なすぎる → 自己資金比率を30%以上に保つ
融資希望額が自己資金に比べて大きすぎると、金融機関は返済リスクが高いと判断します。
自己資金は総開業資金の3割以上を目安に準備するのが理想です。
収支計画が現実的でない → 他院の実績をもとに計画を立てる
収支計画を楽観的に作ってしまうと、実際の経営とのギャップが生じて資金ショートの危険があります。
同業者の実績データなどを参考に、保守的な計画を立てましょう。
返済能力を過信する → 売上見込みを保守的に見積もる
融資が通るとつい安心してしまいがちですが、返済は毎月確実に発生します。
初期の売上見込みは控えめに設定し、無理のない返済計画を立てることが重要です。
接骨院開業の融資を受けるために準備すべき書類とは?
融資を受けるためには、いくつかの書類を事前に準備しておく必要があります。
これらの書類は金融機関によって若干異なることがありますが、基本的には以下の4つが必須です。
創業計画書
接骨院のコンセプト、提供する施術内容、立地条件、競合分析、マーケティング戦略、売上・収支見込みなどをまとめた資料です。
金融機関は、この事業計画書をもとに「この事業は成功するか」「返済能力があるか」を判断します。
できるだけ具体的な数値を盛り込み、現実的な見通しを立てることが重要です。
自己資金の証明書類(通帳コピーなど)
自己資金をどれだけ保有しているかを証明するための書類も必要です。
主に預金通帳のコピーや、金融機関の残高証明書を提出します。
コツコツ積み立てた記録があると、金融機関からの信頼度が上がります。
過去の職務経歴書・資格証の写し
柔道整復師としての経験やスキルを証明するために、職務経歴書や資格証明書のコピーも提出しましょう。
勤務先での実績や評価は、事業の信頼性を高める材料になります。
借入申込書(日本政策金融公庫など所定書類)
各金融機関の指定する借入申込書も必要です。
必要事項を正確に記入し、事業計画書やその他書類と整合性が取れているかを確認しましょう。
接骨院開業の融資の審査に通るためのポイント

融資を受けるには、書類の準備だけでなく、審査に通るための「戦略」も必要です。
ここでは、審査通過率を上げるための4つのポイントを紹介します。
自己資金の割合を高める
融資額に対する自己資金の割合が高いほど、金融機関からの評価は良くなります。
目安としては、開業資金の30%〜40%を自己資金でカバーするのが理想です。
金融機関は「借主がどれだけリスクを取っているか」を重視します。
自己資金が多いということは、本気度や計画性の高さを示す材料となります。
事業計画を具体的に作る
単に「患者が来てくれるだろう」といった甘い見通しでは、審査に通るのは困難です。
競合調査、想定患者数、月間売上、コスト構造などを具体的に数字で示しましょう。
現実的かつ具体性のある事業計画こそが、審査担当者を納得させる鍵となります。
返済シミュレーションを用意する
毎月の返済額が売上の何割に相当するか、余剰資金をどの程度確保できるかをシミュレーションしておくことで、金融機関に「返済計画の現実性」を示せます。
また、金利上昇や患者数減少といったリスクにも備えたシナリオを用意しておくと、さらに信頼性が高まります。
過去の勤務実績や技術力をアピールする
接骨院の開業では、技術や経験がそのまま成功につながる職種です。
今までの勤務実績、得意な施術、地域との関わりなどをアピールしましょう。
「この人なら患者がついてくるだろう」と思わせることができれば、審査も通りやすくなります。
接骨院開業の融資におすすめの金融機関とは?
どこで融資を申し込むかも重要です。
ここでは、接骨院開業に適した4つの金融機関・制度を紹介します。
日本政策金融公庫
創業融資を専門とする政府系金融機関です。
民間の銀行よりも低金利かつ長期返済が可能で、自己資金が少ない場合でも融資を受けやすいです。
特に初めての開業者にとって、もっとも利用しやすい金融機関といえます。
地方銀行・信用金庫
地域密着型の金融機関は、事業の地域性や人柄を重視して審査してくれることが多く、柔軟な対応が期待できます。
また、金融機関によっては、開業後の経営相談やマッチング支援を行ってくれるケースもあります。
商工中金
中小企業や小規模事業者を支援する金融機関で、比較的大規模な設備投資にも対応しています。
信用保証協会の制度を活用した融資も取り扱っています。
一部地域では開業支援プログラムなども充実しています。
自治体の制度融資
都道府県や市区町村が行っている創業支援制度です。
利子補給や信用保証料の一部補助が受けられる場合があります。
各自治体で内容が異なるため、地元の商工会議所や行政窓口に確認することをおすすめします。
接骨院開業の融資を考える前に自己資金はどれくらい必要?

接骨院の開業を成功させるためには、融資だけに頼るのではなく、ある程度の自己資金を準備しておくことが不可欠です。
ここでは、目安となる金額や資金の工面方法について解説します。
総開業資金の30%が目安とされている
一般的に、開業に必要な総資金のうち30%程度は自己資金でまかなうことが望ましいとされています。
たとえば、開業に600万円かかる場合は、180万円ほどを自己資金として準備する必要があります。
これは、金融機関が融資の際に「返済能力」だけでなく、「自己資金の割合」を重視するためです。
日本政策金融公庫の審査通過には100万円以上が理想
日本政策金融公庫を利用する場合、最低でも100万円以上の自己資金があると、審査を通過しやすくなります。
「全額借入でなんとかなる」という考えはリスクが高く、金融機関からの信用も得にくくなります。
少額でも「自分で準備した資金」があることが、計画性と責任感を示す重要な要素になります。
運転資金としても自己資金は必要
自己資金は設備投資や物件費用に使うだけでなく、開業後の運転資金としても活用されます。
患者が安定して通ってくれるようになるまでの期間、収入が少なくても家賃やスタッフの給料などの支出は続くため、自己資金があれば余裕を持った経営が可能になります。
家族や知人からの支援を活用する人も多い
自己資金の一部を、親族や知人からの借入や支援でまかなうケースもあります。
もちろん返済計画を立てたうえで、借用書などを交わすことが大切です。
親族からの資金提供は「信頼の証」として金融機関の評価を上げる要素にもなります。
接骨院開業の融資の返済計画を立てるコツ
融資を受ける際には、ただ資金を得るだけでなく、無理のない返済計画を立てることが成功のカギになります。
ここでは、返済計画の立て方と注意点を紹介します。
開業初期は売上が安定しない前提で計画する
接骨院を開業してすぐに患者が増えるとは限りません。
特に開業から3〜6か月間は、売上が不安定になる可能性が高いです。
この期間の収支が赤字になることを前提に返済計画を立てておくことが大切です。
金利と返済期間を比較して無理のない返済にする
融資には金利がかかるため、返済総額が膨らむことを見越して計画する必要があります。
月々の返済額が高すぎると、経営を圧迫する原因になります。
低金利・長期返済が可能な金融機関を選ぶことが、無理のない資金繰りにつながります。
固定費と変動費を正確に見積もる
返済計画を立てるためには、月々の固定費(家賃、スタッフの給与、光熱費)と変動費(消耗品費、広告費など)を正確に把握することが必要です。
これらをもとに収支シミュレーションを行い、どのくらいの返済額であれば安全に運営できるかを検討します。
余裕を持ったキャッシュフローを意識する
「とりあえず返せればいい」ではなく、キャッシュフローに余裕がある状態を目指しましょう。
突然の設備故障や、急なキャンセルなど、想定外の出費に備えるための資金を常に確保しておくことが重要です。
最低でも3か月分の運転資金をキープすることが望ましいです。
まとめ|接骨院開業の融資を成功させるために大切なこと
接骨院の開業には、数百万円単位の資金が必要となります。
融資を活用することで、資金の壁を乗り越えることはできますが、成功するかどうかは準備と計画次第です。
ここでは、接骨院 開業 融資を成功させるために大切なポイントを改めてまとめます。
明確で具体的な事業計画を立てる
事業計画は融資審査の要であり、開業後の経営指針にもなります。
競合調査・集客戦略・売上予測などをしっかりと盛り込んだ内容を作りましょう。
自信のある事業計画は、金融機関だけでなく、自分自身の支えにもなります。
十分な自己資金を準備する
自己資金は多ければ多いほど融資が通りやすくなります。
また、開業後の経営の安定性にも大きく寄与します。
コツコツと貯蓄をし、必要であれば家族からの支援も検討しましょう。
信頼できる金融機関を選ぶ
日本政策金融公庫や地元の信用金庫など、創業支援に積極的な金融機関を選びましょう。
相談しやすく、開業後も伴走してくれるパートナーを見つけることが大切です。
返済計画を現実的に立てる
返済額が経営の負担にならないよう、保守的な売上予測と長めの返済期間でプランを組むことが理想です。
万が一に備えた余裕のある資金計画が、長期的な経営の安定につながります。
【接骨院・整骨院の開業は柔整開業ドットコムにお任せください】
開業を考えているものの、そこまでのステップが良く分からないという方もいらっしゃるかと思います。
柔整開業ドットコムでは、接骨院・整骨院の開業を全面的にサポートしております。
-
- 事業計画の作成
- 開業場所の選定
- 商圏調査
- 物件の紹介
- 融資の資料作成
- 届出の書類準備
- 治療機器の販売
- ホームページの作成
といったように単なるアドバイスにとどまらず、実際に手を動かし開業準備を進めます。
詳しいご支援内容は以下の記事をご覧ください。

仕事をしている間も私たちが着々と準備を進めますので、今の仕事を続けながら開業の準備が整います。
中には開業の前日まで、仕事を続けていた方もいらっしゃいます。
仕事を辞めてから開業までの期間をかなり短くできるので、収入が途絶えず、安定した生活のまま開業が可能です。
接骨院・整骨院の開業はおひとりでもできます。
ですが、少しでもご不安があればお問い合わせください。
業界20年以上の実績、そして1,512件の開業サポートを支援してきた弊社だからこそ、お伝えできるノウハウがあります。